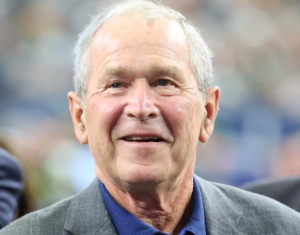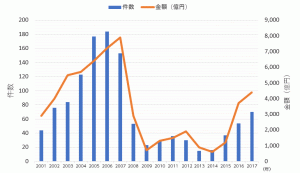進む『日本版SPAC』の真相~“失われた20年”の記憶から見える近未来~
ジョージ・W・ブッシュ米大統領の発言は、その独特な言葉遣いゆえに、「ブッシュイズム(Bushism)」として、様々なウェブサイトでまとめられている(参考)。その中でも、「最も支離滅裂な言葉」として知られているものが、2005年の防衛予算法案についてのスピーチでの次の発言である(参考):
“Our enemies are innovative and resourceful and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.”(我々の敵は革新的で機知に富んでいるが、我々だってそうだ。敵は米国と米国民に危害を加える新たな方法を絶えず考えているが、我々だって同じだ)
確かに支離滅裂ではあるが、海外勢が我が国の「国富」を狙っているという視点において、“They never stop thinking about new ways to harm our country”(敵は我が国に害をなす新たな方法を常に考えている)という部分は「一理あり」と言えそうだ。
(図表:退任後、政治的発言を控えているブッシュ元大統領)
(出典:People)
海外勢の我が国への集中という観点では、気になる動きがある。去る2月2日に公開されたオンライン講演で、木原誠二官房副長官は、未上場企業の買収を目的とした特別買収目的会社(SPAC)の我が国への導入を検討する考えを示したというのだ(参考)。「投資家保護」の観点に留意するとしているが、果たしてその真相はどこにあるのか。
この点で参考になり得るのが、「平成バブル」崩壊後の顛末、すなわち我が国は「失われた20年」の間に海外勢の“草刈り場”となっていたという過去の歴史である(参考)。
具体的には、以下のような流れがあった:
- 1990年代初頭:不動産価格下落の開始
- 1998年:外為法改正
- 2003年頃:「不良債権問題」の最終処理が国政レヴェルで問題化
- 2005年末:「不動産証券化バブル」
- 2007年夏:「サブプライム・ショック」により金融メルトダウン開始
これを見る限り、米欧系のいわゆる“越境する投資主体”は「平成バブル」崩壊後、まずは外為法改正(1998年)によって風穴を開けた後、日本マーケットにおいて「不良債権」を徹底して買うことに成功し、その後に生じた「不動産証券化バブル」の中でこれを「高値」で売り抜けることに成功した、ということが指摘できる。
(図表:開発型証券化の実績)
(出典:大和ハウス工業株式会社)
同じような出来事が今般の「日本版SPAC」でもフラクタルに再現され、我が国は海外勢の“草刈り場”とされる展開となるのであろうか。
そもそも「日本版SPAC」は、昨年(2021年)6月、菅政権の下で閣議決定された「成長戦略実行計画」の中で、その導入検討が明記されたものであるが、成長戦略会議の議事録(参考)によると、麻生財務相(当時)は、SPAC導入について「何となくこの種の新しいものは極めて疑わしいと思う」と否定的な見方を示しているものの、経済産業省の新原浩朗・経済産業政策局長が菅義偉首相にSPACの必要性を訴え、成長戦略に解禁検討を「ねじ込んだ」との情報もある(参考)。菅首相のブレーンとして有名であったデーヴィッド・アトキンソン小西美術工藝社社長も「中小企業の再編」を主張していることからも(参考)、SPACは我が国企業の再編の先にある外資を呼び込むための入口となり得るであろう。
実際に、我が国の企業の中でも、例えばソフトバンクグループ(9984)は、2021年にSPACを利用して米国株式市場に上場している。また、我が国の企業を合併の対象とするSPACとして、「Evoアクイジション」という企業も上場している(参考)。
他方で、SPACの本場である米国においては、規制強化で既にブームは終わったとの向きもある。本来なら上場基準を満たさないような企業が上場してしまうリスクや詐欺事件も頻発しており、米証券取引委員会(SEC)は規制を強化しているのだ。米国においてSPACを興隆させた「SPACキング」として知られるチャマス・パリハピティヤが自身のSPACをめぐり米証券取引委員会(SEC)の調査を受けるなど、SPACを巡る動きは陰転している。また、トランプ前米大統領が設立したメディア企業「Digital World Acquisition」社とSPACの合併計画について、米証券取引委員会(SEC)が調査に入ったとの報道もある中で、その陰には中国資本が入り込んでいるという問題も指摘されており、これはトランプ前大統領としても想定外のことであったとの情報もある。
(図表:元フェイスブック幹部で「SPACキング」と呼ばれるパリハピティヤ)
(出典:VOI)
こうした中で、たとえ我が国で導入されるにあたっても、こうした課題を解決した上で、「投資家保護」の観点が強くなることが想定される。すなわち、かつて米国で盛り上がったSPACのように広く個人投資家が参加できるような話題になる資金調達スキームとはならず、「SPACのようなもの」となる可能性が高い。また、我が国の伝統的な企業の事業再編でSPACが活用することも想定される中で、SPACを通じた我が国の最新鋭技術が吸い出されるという懸念もある。
“They never stop thinking about new ways to harm our country”(海外勢は我が国に害をなす新たな方法を常に考えている)という状況下に我が国がおかれているわけであるが、そうであれば尚の事、“So do we”(我々もそうあれねばならない)でなければなるまい。
グローバル・インテリジェンス・グループ
シニア・アナリスト 原田 大靖 記す

・本レポートは、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。金融商品の売買は購読者ご自身の責任に基づいて慎重に行ってください。弊研究所 は購読者が行った金融商品の売買についていかなる責任も負うものではありません。